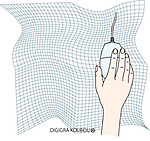写真植字機
印刷と活字の時代は 目まぐるしく変わっていく
1枚1枚の手作業時代の アナログから
大量に情報発信できる デジタルに
活版が 樹脂版になり 印刷もどんどん様変わりしていくが
活字を組む側も変わっていく
とりわけスピードが必要な新聞社は
活版で文字を組み立てていた時と比べて
今では 数倍楽な仕事になっていると思う
その分 また他の悩みや大変さもあるだろうけど…
・
時代の流れの中に 写真植字機の時代がある
写真の技術を用いて 印画紙に文字を焼き込む
黒いガラス板に文字が抜けて 反転で並んでいる
部首別に並んでいたと思うが 日本の文字は多く
ガラス版が 機械の横にも控えていた
それを選んで 文章にしていく
下から光にあてた文字を レンズごしに見ながら
ガラス板をスライドし 目的の文字に焦点を合わせる
カチッ カチッと シャッターを切る
・
随分昔 デザイナーをする前に
新聞社で数ヶ月程 アルバイトをしたことがある
写真植字機を使って 活字を印画紙に焼き付ける
習いながら仕事したので とても苦労した
初めは 容易いものから作成ということで
新聞の読者欄の下のほう出てた囲碁の図
縦列から 横列にすすんで罫と数字記号を原稿通りに
選びながら シャッターを押していく
次は1行タイトルの原稿を 渡される
記事の見出しのことである
原稿が タイトルから文章に変わる
普通に読める文字も 反転となると
1字一句間違わないように 慣れるのに
毎晩 夢でうなされた
・
写植を仕事としていた人は
膨大な文字の山と 種類を知っていて
反転文字を得意とする 職人である
・
・
きょうの一枚